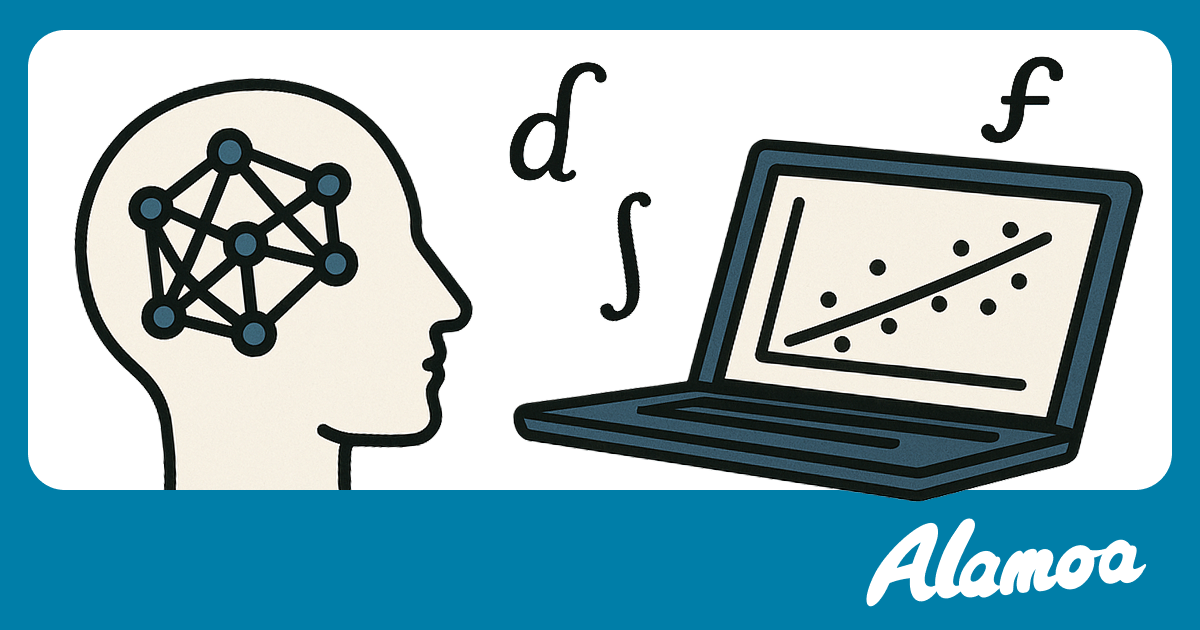
機械学習を始める第一歩 〜AIの裏側を覗いてみよう〜
 高塚 智明(メンター)
高塚 智明(メンター)
2025年8月15日
こんにちは!Alamoa メンターのtomoです。
最近、ニュースやSNSで「AI」という言葉を見ない日はありませんよね。
画像を生成したり、文章を作ったり、翻訳したり…私たちの生活のあらゆる場面で活躍しています。
そんなAIが「どうやって作られているのか?」気になったことはありませんか?
今回は、私が調べて分かった“機械学習のはじめの一歩”についてご紹介します。
AIはどう作られている?
AIの多くは「機械学習(Machine Learning)」という仕組みを使って作られています。
これは、人間がデータを与えて学習させ、そのパターンをもとに予測や分類を行わせる技術です。
例えば、
- 猫と犬の画像をたくさん見せて判別できるようにする
- 過去の売上データから来月の売上を予測する
- 音声を聞き取ってテキスト化する
といったことが可能になります。
ただし、その裏側では様々なアルゴリズムが活躍しています。
アルゴリズムの種類はたくさんある
機械学習の世界には、数えきれないほどのアルゴリズムがあります。
代表的なものを挙げると…
- 回帰(Regression)
数値を予測する。例:家賃の予測、株価の予測 - 分類(Classification)
カテゴリを判別する。例:メールのスパム判定、画像分類 - クラスタリング(Clustering)
似たもの同士をグループ分け。例:顧客層の分析 - 強化学習(Reinforcement Learning)
試行錯誤で最適な行動を学ぶ。例:ゲームAI、自動運転
最初から全てを覚える必要はありません。
むしろ、まずはシンプルなアルゴリズムを一つ選んで、手を動かして試してみることが大切です。
まずは「単回帰分析」から始めよう
私が機械学習を学び始めたとき、最初に触れたのは単回帰分析でした。
単回帰分析は、ある一つの要因(説明変数)から結果(目的変数)を予測する方法です。
例えば、「勉強時間からテストの点数を予測する」ようなイメージです。
ここで登場するのが数学の基礎、微分と積分です。
- 微分:変化の速さを求める(AIの学習過程で「最小誤差」を探すために使う)
- 積分:面積や合計値を求める(理解の背景として役立つ)
高校レベルの微分・積分の基礎が分かっていると、機械学習の仕組みをスムーズに理解できます。
学び方のステップ例
- 微分・積分の基礎をざっくり復習
高校数学レベルでOK。「変化の速さ」と「合計を求める意味」だけ理解すれば大丈夫。 - 単回帰分析をPythonで実装
scikit-learnやnumpyを使って、予測モデルを作ってみる。 - データを変えて試す
身近なデータ(身長と体重、気温とアイス売上など)を使って予測してみる。 - アルゴリズムを少しずつ増やす
重回帰分析 → ロジスティック回帰 → 決定木…とステップアップ。
まとめ
機械学習の世界は奥が深く、最新のAIモデルは非常に複雑です。
でも、最初の一歩は意外とシンプル。
- AIの正体は「データから学ぶ仕組み」
- アルゴリズムは無数にあるが、最初は一つでOK
- 数学は高校レベルの微分・積分が役立つ
- 単回帰分析から始めれば、手を動かしながら理解できる
このステップを踏めば、「AIって難しそう…」という印象が「自分でも作れそう!」に変わるはずです。
Alamoaでも、AI講座を作成中です!ぜひ、一緒にAIの世界に踏み出しましょう!